クリエイターのポートフォリオ。PDFファイルや印刷物として、多くのクリエイターさんが作っていることと思います。より仕事につながるために、ポートフォリオはどのように作ればいいのでしょうか。
クリエイターのポートフォリオは「作品集」ではなく、企業でいうところの「営業資料」であり「商品カタログ」です。この記事では、実際に作りはじめる前に、その基本的な考えかたを整理してみます。
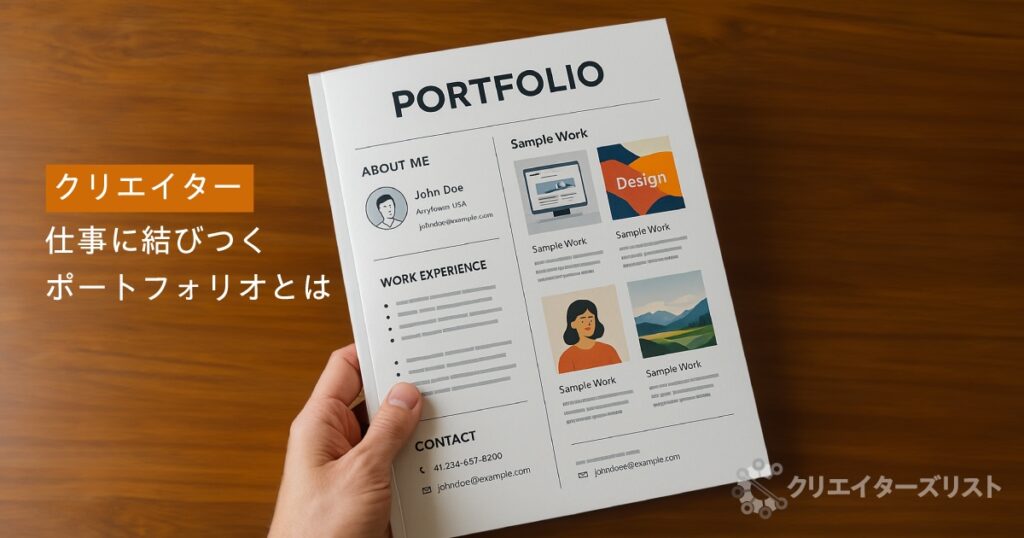
ちなみに、クリエイターのポートフォリオとは、営業ツールとしてPDFや印刷された書類にまとめたものを指します。「ポートフォリオサイト」とは違います。
クリエイターのポートフォリオ、よくある間違い
クリエイターさんのポートフォリオによくみられる、残念な点がいくつかあります。
作品の画像だけ載っていて、言葉が書かれていない
日本語ではポートフォリオ = 作品集と思われているせいか、ポートフォリオにはとにかく作品画像だけを配置し、文字や文章がほとんどないクリエイターさんが多いです。これだと、クライアントは作品を眺めることしかできず、検討ができません。
自己紹介があいまい、または書かれていない
趣味的な自己紹介だけが書かれていて、経歴や実績などの記載がないポートフォリオが多いです。これだと、クライアントは、あなたが信頼できる「仕事人」だとは認識できません。
どうやって仕事を依頼したらいいか、見てもわからない
仕事の依頼方法や値段、受発注の流れなどには一切触れられていないことが多いです。これだと、クライアントは、本当に仕事を依頼して大丈夫なのかが判断できません。
クライアントは、ポートフォリオのどこを見たいのか?
クライアントは、作品を鑑賞したいのではありません。
もちろん作例のクオリティが良いに越したことはありません。ですが、それだけで「この人に頼もう」と決めることはけっしてありません。
クライアントは、ポートフォリオを見て何を判断したいのか。
それは、「この人に頼んでちゃんと仕事が進むかどうか」です。
納期を守れるか、やりとりに無理がないか、業務として安心して任せられるか。ビジネス相手として信頼できるかどうかを、限られた資料の中から判断しようとしています。
作品画像しか載っていないポートフォリオでは、クライアントはその判断ができません。だから仕事の機会を逃してしまうのです。
「作品のクオリティがあまり良くないので依頼されない」というケースは案外少ないといえます。むしろ、作品がいくら良くとも、ビジネス相手として信頼できるかどうかが判断できないので「スルーされている」ことが多いのです。
仕事につながるポートフォリオにしたいなら、入れるべき基本情報
ポートフォリオは作品を鑑賞してもらうための「作品集」ではありません。むしろ、それ以外の部分が本丸です。仕事につながるポートフォリオにしたいなら、次のような情報を載せましょう。
| 個人情報 | 企業と取引したいなら、個人情報を明かさずに信頼が得られるとは思わないほうがいい。実名、居住地を明記するのは最低限の「誠意」と心得て |
| 自己紹介、仕事のプロフィール (経歴) | 趣味的な自己紹介を書くのではなく、これまでの経歴にフォーカスして書く。学歴や職歴といった「事実」をベースに書くとよい |
| 受注実績 | これまでに受注した仕事のリスト。依頼元の企業名や掲載された媒体名などを可能な限り具体的に書く |
| 対応できる仕事内容、得意分野 | 「作品を見てもらったらわかる」とは考えない。言葉や文章で具体的に書く |
| スケジュールの目安 | 依頼から納品までの流れや、それぞれの工程にどのくらいの時間 (日数) がかかるか、という情報を書く。依頼を具体的にイメージしやすくなる |
| 料金表、見積例 | 作業内容ごと、タッチ別などの料金を書く。具体的に書くのが難しいならば「参考価格」や「◯◯円〜」という表記でも。過去の依頼から見積例を掲載するのもよい |
| 依頼方法、連絡方法 | 問い合わせフォームでもメールアドレスでも、あるいは電話でもOK。「依頼や相談はここから連絡してください」とはっきりと書く |
職業別に見る、伝えるべきポイントの違い
ポートフォリオに載せる情報は、職種によって伝えるべき内容が少しずつ異なります。「自分がどこまで関わった仕事なのか」「何を目的にどう作ったのか」を、相手が判断しやすいように言葉で補足しましょう。
ウェブ制作者
- 担当範囲を明記する (例: ワイヤーフレーム設計、デザイン、実装、CMS構築など)
- 技術的な説明も補足する (例: 使用した言語、CMS、レスポンシブ対応など)
- 「問い合わせ数が増えた」などの成果がある場合は簡単に数字を添えると伝わりやすい
グラフィックデザイナー
- クライアントの業界、業種、目的 (例: 集客、ブランディング、説明など) 、ターゲット
- どんな依頼内容に対して、どんな意図でデザインを組み立てたかを文章で書く
- 制作物のモノとしての詳細 (サイズ、製造工程など)
ライター
- 掲載媒体 (例: 企業ブログ、業界誌、ニュースメディア)、読者層・テーマ
- 文字数、取材方法 (オンライン/現地)、執筆目的 (SEO/広報など) なども加えると説得力が増す
イラストレーター
- イラストが使われた媒体 (雑誌、書籍、広告、ウェブサイト、製品など) と目的
- どのような依頼があり、要望に対してどのようなものを提案したか、どのようなトーンを求められたか、などを補足する
写真家
- 写真が使われた媒体と使用目的 (ウェブ用、印刷物、広告など)
- どのような依頼があり、要望に対してどのようなものを提案したか、どのようなトーンを求められたか、などを補足する
- 撮影条件 (屋外/スタジオ/自然光など) や、演出・加工の有無も書くと仕事の幅が伝わる
全体的に、「これはどういう仕事だったのか?」が言葉でもわかるようにすると、依頼側は「自分もこういうの頼めるかも」と想像しやすくなります。
よいポートフォリオ・悪いポートフォリオの違いとは?
ポートフォリオは、たいていのクリエイターさんが作っているでしょう。でも、仕事が来る人と来ない人がいます。
その差は、作品のクオリティではありません。クライアントからみて依頼しやすいと思えるかどうか、つまり、相手にとって親切かどうかで結果が分かれるのです。
その違いのポイントを挙げてみました。あなたはいくつ当てはまるでしょうか? ポートフォリオをブラッシュアップするときのチェックリストにしてみてください。
悪い例: 見た目はキレイ。でも仕事の資料としては機能してないポートフォリオ
- 作品画像ばかりで、文字がない。どんな仕事だったのかがわからない
- 自己紹介に「◯◯の作品が好きです」といった個人的な趣味の話がたくさん書いてある
- 名前っぽいのが載ってるけど、屋号なのかアカウント名なのかなんだかよくわからない
- 料金や納期がわからず、依頼したらどうなるか想像できない
→結果: 「作品はすごいけど、仕事任せるのは……あんまりにも不安すぎる……」とスルーされてしまう
よい例: 「この人に頼めばちゃんとやってくれそう」と思わせるポートフォリオ
- 各作例に制作背景、目的、担当範囲などの情報が添えられている
- 経歴や実績がまとまっていて、何が得意な人なのか伝わる
- 個人情報と連絡先、どこの誰なのかがはっきり書かれているので、安心して連絡を取れる
- 依頼方法、参考料金、スケジュールなどが書かれているので、依頼したあとのことがイメージできる
→ 結果: 「あ、これならお願いできそう」と、問い合わせ・依頼につながる
FAQ (よくある質問、疑問)
Q. とにかく美しい作品集を作れば、感動した人が仕事をくれるかもしれないのでは?
企業に勤めている人が「これすごい!」という感動だけに突き動かされてクリエイターに依頼することは、ありません。なぜなら、その人には会社のお金を預かって制作をするという重い責任があるからです。
もし作品自体に感動したとしても、「で、この人に頼んだらどうなるの?」「ちゃんと仕事してくれるの?」「いくらなの?」「納期はいつ?」がわからなければ、不安で依頼できません。だから、ただ美しい作品集を作ってもダメなのです。
Q. 文字を入れすぎると、世界観が壊れませんか?
世界観や個性にこだわるよりも、ただ情報を掲載することの方が、仕事を獲得するためには効果があります。だから情報 = 文字や文章は必須です。
そのうえで、よりこだわりたいのであれば、文字や文章が入っていても世界観を壊さないデザインを考えましょう。できないならば、そのスキルを身につけましょう。他のデザイナーにお金を払って依頼してもかまいません。
Q. 実績がまだ少なくて、載せられるものがほとんどありません……。
次のステップに進むためには、小さくてもいいので、具体的な実績をひとつでも載せることが重要です。知り合いからの依頼や、知っているお店からの依頼でもかまいませんので、その依頼主の名前、業種・業界、依頼内容を書きましょう。
どんな依頼に対し、どんな仕事を返すことができるのか、それが伝わることが大切です。
実績が少ないうちは、自主制作や架空の案件を載せてもいいですが、ポイントは同じです。ただ作品を載せるのではなく、たとえば、「飲食店のメニュー表を想定して作ったデザインです」など、想定の依頼内容と狙いを文章として添えます。そうすれば仕事の材料になれる可能性があります。
Q. 料金を出すと、安く値切られそうで怖いんですが……。
むしろ、逆です。料金を書いておくことにより、「皆様にこの値段で提供しておりますので」という説明ができ、値切られそうになった際の交渉材料になります。
「クリエイターに依頼したいが、値段がわからないのでハードルが高い」という声はいまなお根強いものです。「これくらいが目安ですよ」という情報は、相手への親切でもあります。
Q. スケジュールの目安って、どう書けばいいんですか?
「初回の打ち合わせから2週間ほどで初稿提出」など、大まかな流れでOKです。
仕事によっていろんな条件がありますので、1日単位で細かく書くのはさすがに難しいと思います。クライアントとの連絡や確認作業などを抜いた、制作作業だけでだいたいどのくらいかかるか、といった情報で十分です。
Q. オシャレなデザインにこだわりたい気持ちと、読みやすさってどっちを優先すべき?
いうまでもなく、読みやすさです。
オシャレすぎて読めないのは本末転倒です。やたらと文字の色が薄かったり、やたらと文字が小さかったりするのは絶対に避けてください。なぜなら、文字を読まれ、内容を理解されることが仕事につながるからです。読みやすく、かつオシャレなデザインを考えてください。
相手に伝わることが最優先。見た目にこだわってもいいですが、営業資料としての役割を忘れてはいけません。
まとめ: 仕事を呼ぶポートフォリオは、信頼と判断材料のかたまり
クライアントからみて「このクリエイターは信頼できそう」と思えること。
それが仕事を呼ぶポートフォリオの本質です。
人は、ただ作品を見せられて、「うまいね」「すてきだね」とは思えても、「この人は信頼できる」とは判断できないのです。だから、ポートフォリオには情報が必要なのです。「私は実績あるクリエイターなので、信頼してもらって大丈夫ですよ」と伝わるように、ここで述べたような情報を載せましょう。
あえていいますが、ポートフォリオは「作品集」ではありません。あなたという仕事人クリエイターの「営業資料」であり、「商品カタログ」です。
ぜひ、このように発想を切り替えてみてください。よりよい仕事が舞い込んでくることと思います。
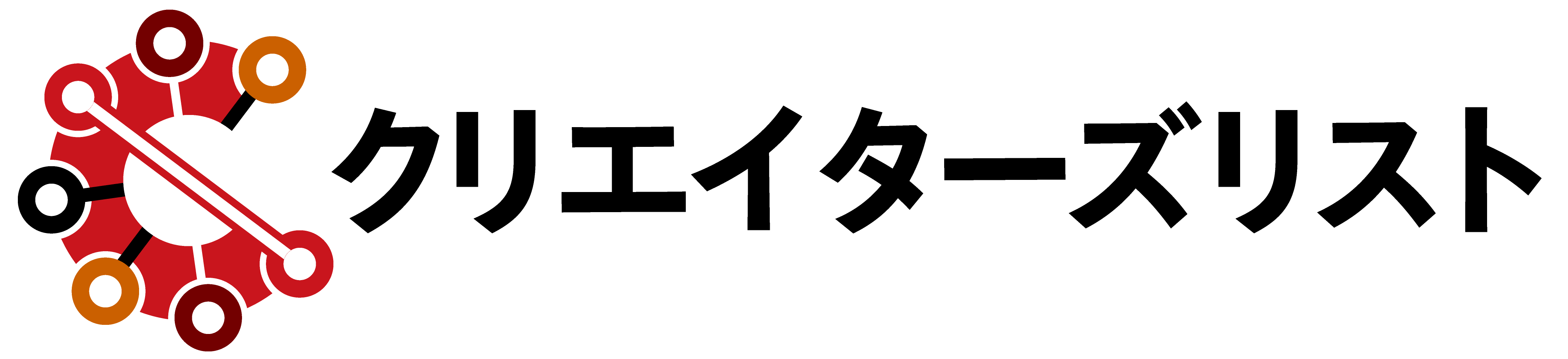
![クリエイターのポートフォリオの作り方。ツールや体裁は? [実践編] クリエイターのポートフォリオの作り方。ツールや体裁は?](https://creatorslist.jp/wp-content/uploads/2025/08/tools-and-appearances-for-a-creators-portfolio-practical-main@2x-80-150x150.jpg)
![第3回みやスタビジネスプランコンテストで「クリエイターズリスト」について発表しました[2025年2月12日 西宮商工会館] クリエイターズリスト 第3回みやスタビジネスプランコンテスト発表資料](https://creatorslist.jp/wp-content/uploads/2025/06/アートボード-1@2x-150x150.png)
